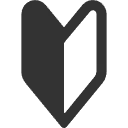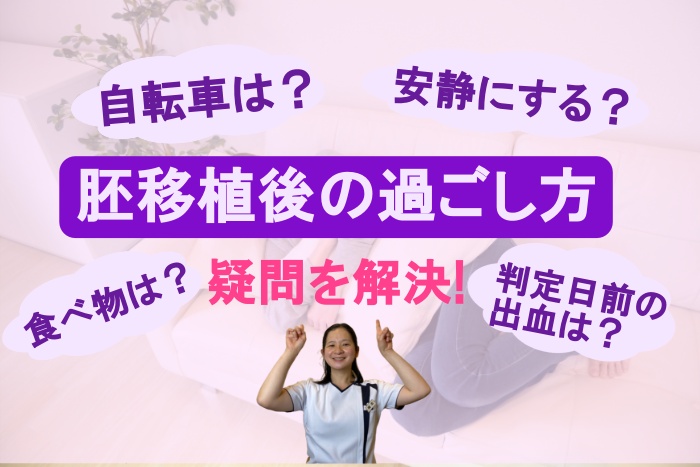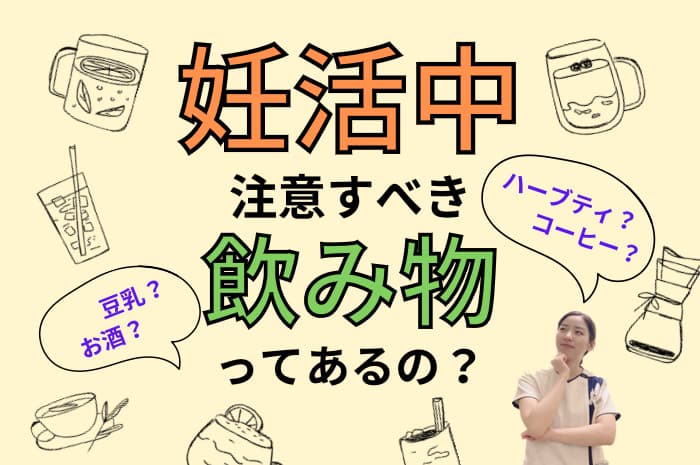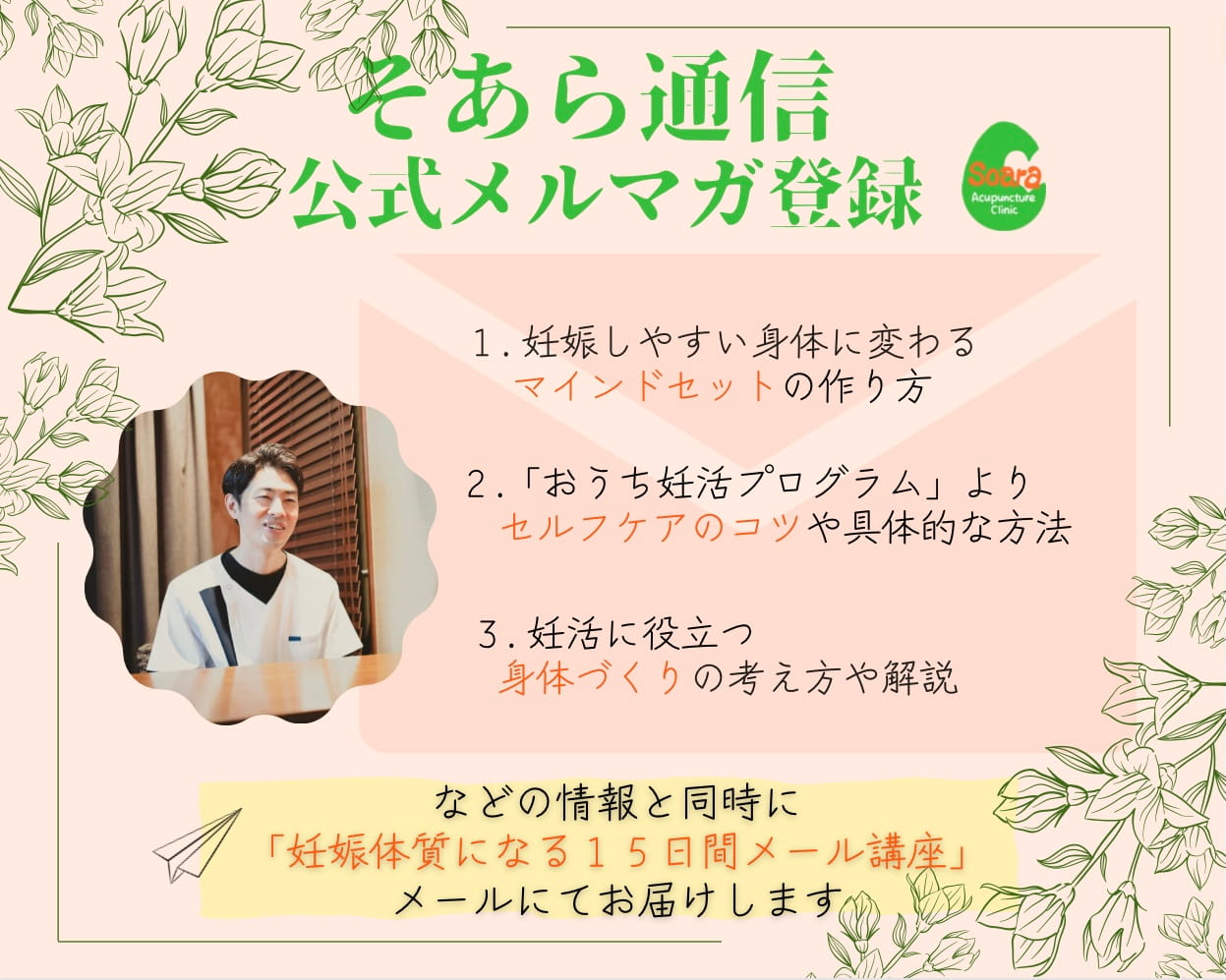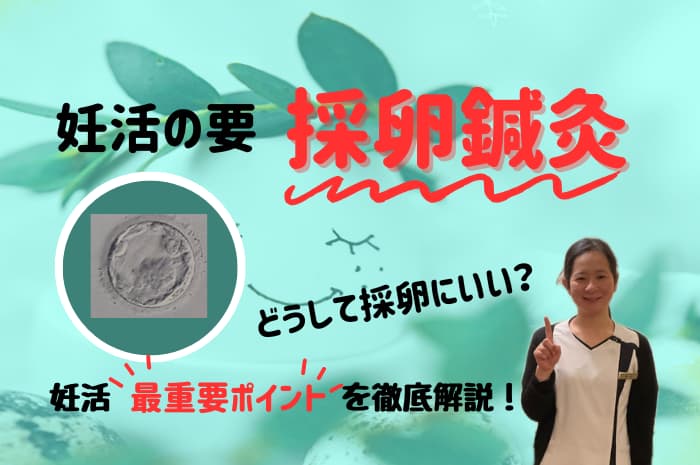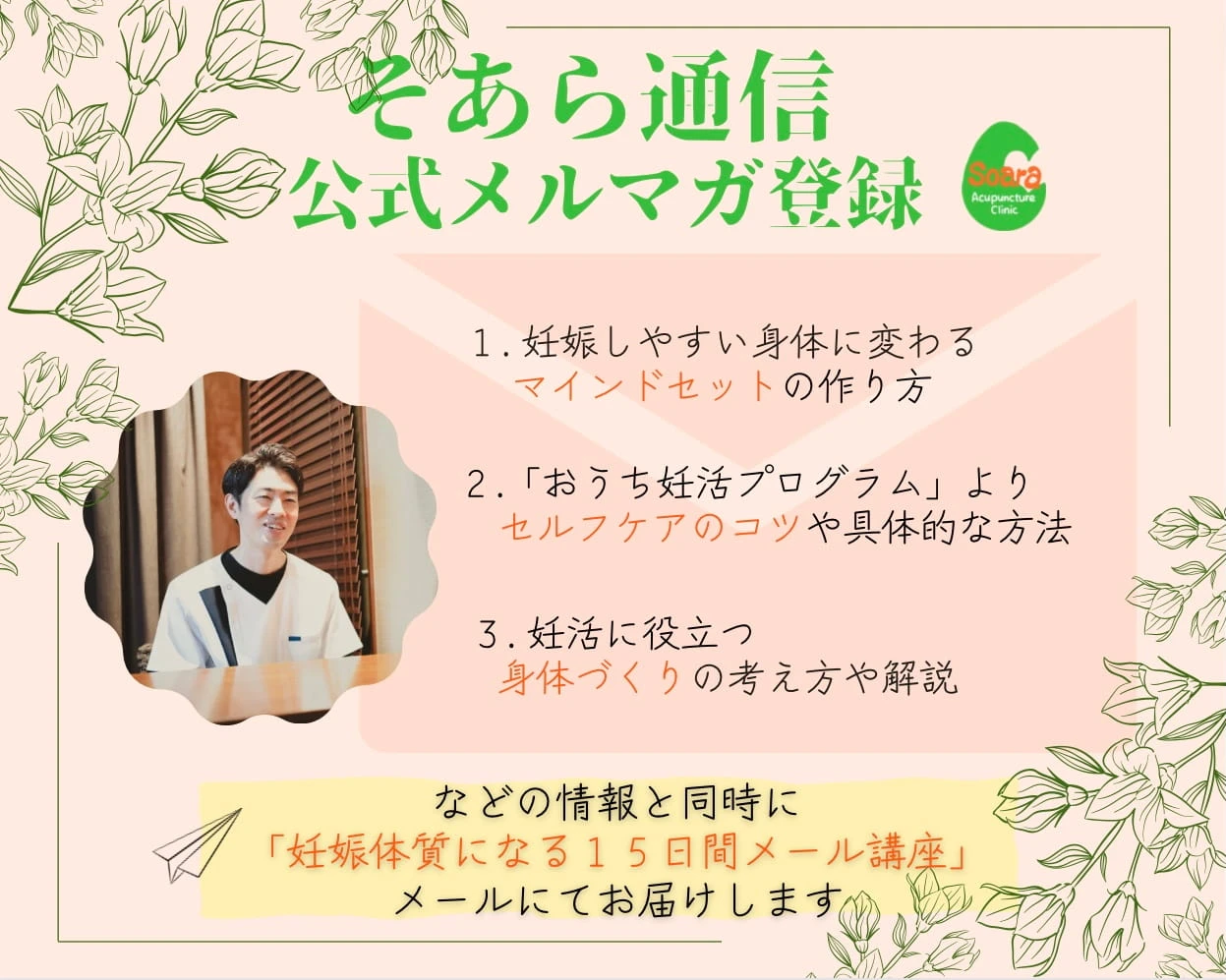妊活お役立ちコラム
2025/07/04
おうち妊活
妊活中もお酒を飲んでもいい?!飲んで良いとされる量は?

妊活中、「お酒を飲んでもいいですか?」というご質問はとてもよくいただきます。
リフレッシュしたい時に飲みたくなることもあれば、人付き合いの場面で、飲まないと雰囲気が悪くなってしまうから…と悩まれる方もいらっしゃいます。
妊活をしていく上で、お酒が妊活や妊娠にどんな影響を与えるのかを知っておくことはとても大切です。
今回は、妊活中にお酒を控えた方がいい理由、影響を最小限にする工夫などを詳しくお伝えしていきます。
【もくじ】
- 01妊活中にお酒を控えたほうがいい理由
- 02アルコールを飲んでも影響のない量はあるのか?
- 03お酒を控えるべき時期
- 04胎児への影響
- 05妊活中の男性もお酒を控えたほうがいい理由
- 06お酒以外に控えたほうが良い飲み物
- 07妊活中におすすめの飲み物
- 08お酒を飲む際の注意点
- 09そあら鍼灸院の考え
- 10まとめ
妊活中にお酒を控えたほうがいい理由
妊娠したらお酒は控えた方がいいと言われています。
お酒が胎児に影響を及ぼし、
中枢神経障害や顔面奇形などの障害が出る可能性があるためです。
量に関してはこれ以下の飲酒量であれば胎児に影響がないという安全量は確立されていません。
そのため、妊娠が分かった時点で禁酒をするのがベストという事となります。
しかし
一般的に体外受精の移植後には飲酒を控えた方が良いとされていますが、それより前の時期の飲酒は規制されていません。
この記事ではアルコールを摂取することでどのような影響があるのかを解説します。
そもそもお酒の適量とは?

通常のアルコール代謝能を有する日本人においては「節度ある適度な飲酒」として、1日平均純アルコールで約20g程度である旨の知識を普及する。
厚生労働省 「アルコール」
https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b5.html(2025年6月24日閲覧)
厚生労働省が推進する国民健康づくり運動で掲げているアルコールの分野では、
日本での適量とは1日当たりアルコール20gとされています。
それ以上摂取すると
- ・生活習慣病のリスクが上がる
- ・早期に肝硬変やアルコール依存症になりやすい
- ・エストロゲンのバランスが崩れやすくなる。
- ・不妊症のリスクが上がりやすくなる。
などが現れる可能性があります。
アルコール20gの目安として
- ・ビール(アルコール度数5%):500ml
- ・日本酒(アルコール度数15%):180ml
- ・焼酎(アルコール度数25%):約110ml
- ・ウイスキー(アルコール度数43%):60ml
- ・ワイン(アルコール度数14%):約180ml
もしご自身で調べたいときはこちらを参考にに当てはめて計算することができます。
【計算の仕方】
お酒の量(ml)×[アルコール度数(%)÷100]×0.8
例)ビール中びん1本 500×[5÷100]×0.8=20
そうは言っても、この量は目安となります。お酒を飲むとすぐ顔が赤くなる人など個人の体質によって、20gいってなくても体調が崩れてしまう方もいらっしゃるので様子を見ながら飲むのが一番です。
週に50gのアルコール摂取は妊娠にマイナスの影響を示唆
こちらの論文を紹介します。
週50g以上のアルコールを摂取する女性集団における平均摂取量である50gで二分した。50gは約4杯分に相当する。週4杯以上摂取した女性は、週4杯未満しか摂取しなかった女性と比較して、生児出産の確率が16%低かった(オッズ比0.84、信頼区間0.71~0.99、表2)。特に、白ワインを毎週摂取する女性は、生児出産の確率が低下することが観察された(オッズ比0.83、信頼区間0.70~0.98)。
男性の飲酒全体と生児出生率の間には統計的に有意な関連は認められなかった(OR 0.90; CI 0.79–1.03)が、ビールを毎日飲む男性では生児出生率のオッズが35%低かった(OR 0.65; CI 0.48–0.89)(表3)。
さらに、夫婦の両者が週に4杯以上飲酒するカップルでは、両者が週に4杯未満しか飲酒しないカップルと比較して、生児を得る確率が21%低かった(OR 0.79、CI 0.66-0.96)(図1)。
結論として、体外受精周期開始時の男女のアルコール摂取は、周期の結果、特に受精不全および生児出産に悪影響を及ぼす可能性があります。少量のアルコール摂取(週4杯)でも、悪影響の増加が観察されたことは特筆に値します。体外受精周期の結果に影響を与える要因は数多くあり、例えば年齢などは患者がコントロールすることはできません。しかし、アルコール摂取は修正可能なリスク要因であり、体外受精周期開始前に患者にアルコール摂取を減らすか、または中止するようカウンセリングを行うことは、周期の成功に寄与する可能性があります。(Yahoo翻訳)
Brooke V Rossi 1, Katharine F Berry 1, Mark D Hornstein 1, Daniel W Cramer 1, Shelley Ehrlich 1, Stacey A Missmer 1 “Effect of Alcohol Consumption on In Vitro Fertilization“【体外受精に対するアルコール消費の影響】
Nationnal Library of Medicine
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4487775/
体外受精を受ける女性で、週にアルコールを50g以上飲むと、生児出産の確率が16%低下。
男性では全体的な飲酒と出産率に有意差はなかったものの、ビールを毎日飲む男性は出産率が35%低下。
夫婦ともに週4杯以上飲む場合は、出産率が21%低下しており、カップル単位での影響も確認されたとされています。
つまり、週に50gの飲酒によって、体外受精の成功率を下げる可能性があり、飲酒はコントロール可能なリスク要因のため、体外受精前にはアルコールの制限や中止が望ましいとされています。
お酒と酸化ストレス(抗酸化様物質の摂取も意識する)
アルコールを過剰摂取すると、酸化ストレスを引き起こしやすくなります。
アルコールは2種類の酵素の働きにより、速やかに水と二酸化炭素に無毒化され体外へ排出されます。その過程で生み出されるアセトアルデヒドは、活性酸素を発生させてしまいます。
この活性酸素が、卵子や精子を傷つける「酸化ストレス」の原因に。
しかし、活性酸素とは体内に侵入した病原体やがん細胞などを攻撃・分解するという良い役割も担っています。
通常はこの活性酸素と活性酸素を除去する抗酸化作用とでバランスが取れた状態ですが、アルコールを過剰摂取してしまうとそのバランスが崩れてしまうことで卵子の老化や酸化を促してしまうのです。
特にたくさん飲む方は、注意が必要です。
アルコールを飲んでも影響のない量はあるのか?
そうはいっても妊活中、お酒を飲みたくなる場面もあると思います。
またこのような論文もあります。
私たちの結果は、不妊治療開始前の 1 年間におけるアルコール (例: ≤12 g/日) およびカフェイン (例: <200 mg/日) の低~中程度の摂取が ART の中間結果または臨床結果に悪影響を及ぼさないことを保証しています。(Yahoo翻訳)
L Abadia , Y-H Chiu , P L Williams , T L Toth , I Souter , R Hauser , J E Chavarro , A J Gaskins ; EARTH Study Team “The association between pre-treatment maternal alcohol and caffeine intake and outcomes of assisted reproduction in a prospectively followed cohort”【前向き追跡コホートにおける治療前の母体アルコールとカフェイン摂取と生殖補助医療の結果との関連】
Nationnal Library of Medicine
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28854726/
こちらの論文では、不妊治療開始前の1年間におけるアルコール量1日12g(5%のアルコール300mlくらい)以下の摂取はART(生殖補助医療技術)に悪影響を及ぼさないとしています。
お酒を控えるべき時期
妊活や不妊治療中で、時期によっては飲酒を避けた方が望ましい時があります。
排卵の可能性がある時期以降
排卵時期はホルモンがガラッと変わりやすい時期となります。
それに応じておりものの変化や腹部の痛み、体温の上昇、だるさ、胸の張り、精神的な変化なども出やすいため、このような症状が飲酒によって悪化してしまう可能性があります。
また、排卵時期は女性ホルモンのエストロゲンが高まってきます。
アルコールは肝臓で代謝されますが、エストロゲンも肝臓で代謝されます。
排卵時期にお酒を飲むとアルコール分解が優先され、エストロゲンの代謝が疎かになってしまいます。
その結果、血中エストロゲン濃度は上昇し、ホルモンバランスが崩れてしまう場合もあるため、この時期での飲酒は控えた方がいいです。
移植前後以降
移植周期は妊娠しやすい子宮環境を作るうえで大事な時期となります。
そのためコンディションを整えるためにも、移植前1週間くらいからお酒は避けた方が望ましいです。
また移植後は妊娠の可能性があるため、控えましょう。
移植後の過ごし方はコチラ
胎児への影響
妊娠中はアルコール厳禁‼︎と言われている理由としてアルコールが赤ちゃんへ負担となってしまうからなのです。
妊娠中にお酒を飲むと、胎盤を通して赤ちゃんへアルコールが運ばれていってしまいます。
赤ちゃんへ運ばれたアルコールは肝臓で処理されるのですが、まだ未熟な肝臓です。
そのためうまく処理できないこともあり、早産や流産の原因となってしまう場合があります。
妊娠初期の飲酒のリスク
赤ちゃんの器官形成期である妊娠初期での飲酒は、流産のリスクがより上がってしまいます。
それと共に「胎児性アルコールスペクトラム障害(FASD)」と呼ばれる発達障害のリスクを高める可能性があります。
胎児性アルコールスペクトラム障害(FASD)
胎児性アルコールスペクトラム障害(FASD)とは、妊娠中の母親の飲酒が胎児に与える影響を総称した言葉です。
特徴的な顔貌や低体重、中枢神経系の障害などがみられ、中枢神経系への影響は一生涯続く可能性があります。
FASDには、胎児性アルコール症候群(FAS)も含まれ、特徴的な顔貌、発達遅滞、中枢神経系の障害の3つが揃うとFASと診断されます。
これらは妊娠中の飲酒さえなければ、産まれてくる子にこの症状は絶対に出ません。
そのため妊娠がわかったら、飲酒は避けるべきなのです。
妊活中の男性もお酒を控えたほうがいい理由
男性は適度なアルコール摂取であれば、妊娠率に関係ないとされています。
しかし一方で、毎日多くのアルコール量を摂取した時やアルコールが強くない・弱い方は、通常よりも総精子運動率、進行性精子運動率、総運動性精子量が有意に低いと掲載されている論文もあります。
112人の男性のうち、45人(40.2%)がALDH2 (ミトコンドリアアルデヒドデヒドロゲナーゼ2)キャリアでした。ALDH2*2キャリアの中で、アルコール摂取は、総精子運動性(中央値20%[四分位間範囲11%-42%]対43%[IQR 31%-57%]、p=0.005)と進行性精子運動性(19%[IQR 11%-37%]対36%[IQR 25%-53%]、p=0.008)の有意に関連していた。アルコール消費者の中で、ALDH2*2キャリアは、ALDH2*1/*1の個人と比較して、総精子運動量(20% [IQR 11%--42%]対41%[IQR 19%-57%]、p=0.02)、進行性精子運動性(19%[IQR 11%-37%]対37%[IQR 17%-50%]、p=0.02)、および総運動性精子数(2800万[M; IQR 9-79M]対71M [IQR 23-150M]、p=0.05)が有意に低かった。第二に、ヒト精子におけるALDH2発現は、ALDH2*2キャリアにおいて有意に低かった(Yahoo翻訳)
Daniel R Greenberg , Hriday P Bhambhvani , Satvir S Basran , Brett P Salazar , Luis Carl Rios , Sin-Jin Li , Che-Hong Chen , Daria Mochly-Rosen , Michael L Eisenberg “ALDH2 Expression, Alcohol Intake and Semen Parameters among East Asian Men”【東アジア男性におけるALDH2発現、アルコール摂取、精液パラメータ】
Nationnal Library of Medicine
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35344413/
112人の男性のうち、45人(40.2%)がALDH2*2(エタノールの代謝産物のアセトアルデヒドを分解する主要な酵素が遺伝的に分解能力の低い型。要は「お酒に弱い体質」。)キャリアである。
ALDH2*1/*1(要は「お酒に強い体質」)とALDH2*2キャリアを比較して、総精子運動量、進行性精子運動性、および総運動性精子数が有意に低かったとしています。
慢性的なアルコール使用は、週に≥350mLのビールの消費または他のアルコール含有飲料の対応する量によって定義されました。
慢性的なアルコール使用は、非飲酒者の33.9 ± 18.0%と比較して、SDFIを49.6±23.3%に増加させました。(Yahoo翻訳)
Akira Komiya , Tomonori Kato , Yoko Kawauchi , Akihiko Watanabe , Hideki Fuse“Clinical factors associated with sperm DNA fragmentation in male patients with infertility”【不妊症の男性患者における精子DNA断片化に関連する臨床的要因】
Nationnal Library of Medicine
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4137616/
SDFIとは、精子DNA断片化指数(sDFI、DFI検査とも書かれたりします)で、DNAにダメージがある精子の割合を示すものです。
この数値が高い場合では、受精率、胚発生率、妊娠率が低下したり、流産のリスクが高くなったりすることがあると言われています。
週350mL以上のビールなどのアルコール摂取が「慢性的な飲酒」と定義されていて、その習慣がある人では、非飲酒者と比べて精子DNA断片化指数(SDFI)が有意に高く(約50% vs 約34%)、精子の質が低下することが示されています。
そのためアルコールに強い体質だから飲んでもいいわけでなく、習慣的にアルコールを摂取すると精子のDNAにダメージを与える可能性があると言う事です。
精液所見が問題ない方も精子の質を上げる生活習慣を送ることが、不妊治療の成功への良い流れとなります。
そのため妊活中はお酒の量を控えた方が良いかもしれません。
お酒以外に控えたほうが良い飲み物
今までお酒にフォーカスして話していきましたが、お酒以外でも気をつけた方が良い飲み物もあります。
カフェイン

カフェインが入った飲み物は、摂りすぎないように気をつけた方が良いです。
理由としてカフェインを摂り過ぎる(1日500mg以上)と、不妊症のリスクがあがる可能性があるからなのです。
一般的にカフェインが入った飲み物は、コーヒー、お茶、紅茶、ココア、コーラ、エナジードリンクなどです。
しかし一方で、眠気覚ましや集中力upなどの目的で飲まれる方も少なくないのではないでしょうか。
もし飲みたい場合は、カフェインを除いたデカフェやノンカフェインのコーヒーを購入するのもおすすめです。
出先などで無い場合は、1日カフェイン200mgまで(コーヒーでしたら2杯程度)でしたら妊活中でも問題ないとされていますので、
量を気をつけながら、摂取してもらえたらと思います。
控えたほうがいい飲み物については、こちらの記事もご参考にしてください。
エナジードリンク
エナジードリンクは、カフェインに加え糖が多く含まれています。
それだけ身体への影響も増えてきます。
そのためエナジードリンクの摂取はできるだけ控えたほうがいいです。
甘い飲み物
糖分の多い甘い飲み物は摂取後血糖値が急上昇します。
急上昇した後は、血糖値をもとの状態に戻そうとインスリンが過剰に分泌された結果、血糖値の乱高下が起こります。
それが自律神経を乱してしまう可能性もあります。
自律神経が乱れるとホルモン分泌に影響したり、血流を悪くしたりなど、子宮や卵巣に必要な栄養・酸素が届きにくくなり、妊娠しやすい身体づくりが妨げとなるのです。
甘いものは飲み物に限らず、スイーツにも関連してくるので、注意が必要です。
こちらも参考にしてみてください。
冷たい飲み物
冷たい飲み物は身体を冷やしやすくしてしまいます。
身体が冷える事で血流が乱れ、子宮や卵巣に栄養やホルモンが届きづらくなってしまいます。
すると、妊娠しづらく身体の状態になってしまう可能性もあり得るのです。
妊活中におすすめの飲み物
妊活中におすすめな飲み物を紹介します。
水
私たちの身体の中で1番多いものが水分。
水分がある事で、栄養素を必要な場所へ運び、老廃物を排出することができるのです。
日常生活で呼吸や汗、便・尿により約2.5lくらい身体から水分が出ていくと言われています。
そのため水分摂取はとても重要です。
さらに一気に飲まず、こまめに飲んであげることで胃の負担も無く、水分を吸収しやすくなります。
体格や活動量にもよりますが、少なくても1日1.5lくらいは飲むように心かげましょう‼︎
カフェインの入っていない飲み物
ノンカフェインの飲み物には、麦茶、ルイボスティー、黒豆茶、タンポポ茶などがあります。
ルイボスティーには抗酸化作用をもつポリフェノールが含まれており、黒豆茶には血流をサポートする成分(アントシアニンなど)が含まれています。
体調や目的に合わせて、飲み分けるのもおすすめです。
妊活中のオススメの飲み物
お酒を飲む際の注意点
妊活や不妊治療中にお酒を楽しむ際、以下の部分を注意してあげると、身体への負担が軽減しやすくなります。
飲酒量を守る
妊活中に限らず、お酒の飲み過ぎは身体への負担が高くなります。
上記でお伝えしたように飲む量としての適量は、
「純アルコールで約20g程」となります。
この適量は必ずしも一定ではありません。
お酒を飲むとすぐ顔が赤くなってしまう方はこれよりも少ない量が推奨されますので、自分に合った飲酒の量を意識しましょう。
糖質が低いお酒にする
糖質が高いお酒ですと、口当たりも良く飲みやすいので、飲む量も増えがちになってしまいます。
それに糖質の多いお酒(ビール、日本酒、甘いカクテルなど)は、甘い飲み物同様に血糖値の乱高下が起こり、自律神経の乱れを引き起こす可能性もあります。
そのため、飲むとしたらできれば糖質の少ないウイスキー、焼酎、辛口ワインなどの糖質の低いお酒を意識するだけでも違うと思います。
お酒の中でも、温めるお酒冷やすお酒あるのでこちらも合わせてご覧ください。
夜遅い時間の飲酒は避ける(早めの時間に飲む)
実はお酒を飲んで寝てしまうと、アルコール分解速度が半分に落ちしまうと研究で報告されています。
しかも睡眠の質を下げてしまう影響もあるのです。
「お酒を飲むとすぐに眠れる」と言われる通り、お酒を飲むことで寝付くまでの時間短縮、深い睡眠の増加という働きがあります。
しかし睡眠の後半ではガラッと変わり、深い睡眠が減り、眠りが浅くなることで途中で起きてしまうことも増えるのです。
そのため、飲酒をする時は早い時間から飲み始め、飲んだあとはしっかりと水分を飲み、アルコール分解がし終わった後に眠りに着くつくことが大事です。
睡眠の質を上げるための習慣はこちら
おつまみを工夫する
お酒を飲んでるとついつい箸が進んでしまうおつまみ。
唐揚げやフライドポテト、〆のラーメンなど意外と脂質や糖質が多くなりがちになります。
摂取した物は肝臓で中性脂肪となりエネルギーをとして各所で消費されますが、中性脂肪が増えてしまうと肥満の原因となります。
体重を増やしすぎてしまうと排卵がスムーズにいかなくなることも。
そのため、糖質やカロリーの控えたおつまみを取るよう意識してみましょう‼︎
亜鉛も摂取する
実はアルコールを代謝するために必要な酵素は、亜鉛を材料としています。
また、亜鉛は妊活にも重要な働きをしています。
卵胞刺激ホルモン(FSH)や黄体形成ホルモン(LH)の働きを高めたり、亜鉛が不足すると排卵がスムーズに行われなかったりと、排卵や着床に関連する多くのホルモンに亜鉛は必要となるのです。
そのためアルコールを飲む際は、亜鉛が豊富に含まれる牡蠣などの魚介類や豚レバーなどの肉類をおつまみに意識するのも良いでしょう。
亜鉛の記事はこちら
パートナーや専門家に相談する
妊活中は、夫婦で一緒に取り組むことが大事です。
よく相談を受けることとして、
「自分は飲みたいのを我慢しているのに、相手が毎日飲んでいて帰りが遅い。妊活は2人で望んだ事なのに、自分だけが我慢している気がしてイライラしてしまう」
などあります。
上記でお伝えしたように、アルコールは女性も男性にも影響が起こる可能性があります。
そのため夫婦間でも話し合いをし、一団となって取り組むことで妊娠への近道となるはずです。
それでも難しい場合は、専門家に相談するのも良いと思います。
そあら鍼灸院の考え

アルコールについては鍼灸の中でも一人一人によって、対処が異なります。
どんな種類のお酒をどれくらい飲むのか。
またお酒を飲む方の体質などなど…
一般的に、良くビールを飲まれる方は手足の冷えが起こりやすくなります。
またアルコールを摂取することで胃腸の負担が強くなり、むくみなど起こしている場合も多いです。
内臓の不調は身体全体の流れが悪くなってしまい、卵巣や子宮にも影響を起こしやすいです。
そのため妊活を始める場合は、お酒の量を減らしてあげた方が内臓の働きも活発になり、妊活にもプラスに働きやすいかと思います。
まとめ
妊活中にお酒を控えた方がよい理由として
妊娠初期の飲酒は、胎児の「中枢神経障害や胎児性アルコール症候群(FASD)」のリスクを高めるためです。
そのため、妊娠が分かった時点で安全な飲酒量は確立されておらず、完全に避けるのが基本です。
妊活中でも、週4杯以上(純アルコール50g以上)の飲酒で生児出産率が16〜21%低下したとの報告もあるため、移植周期や排卵期以降などのタイミングでは、控えるのが望ましいとされます。
男性側の飲酒も重要なポイント
一見、男性の飲酒は影響が少ないと思われがちですが、
特にお酒を飲むと顔が赤くなってしまうようなALDH2(アセトアルデヒド分解酵素)活性が低い体質の方では精子運動率が有意に低下したとの研究があります。
精子の質を整えるためにも、パートナーも飲酒を見直すことが妊娠への近道です。
そうは言っても妊活中のお酒は、絶対ダメというわけではありません。
しかし、妊娠の可能性がある時期や治療周期中など、タイミングや体調に応じて賢く選ぶことが重要です。
飲みたいときの工夫
- ・糖質の少ないお酒(焼酎、ウイスキー、辛口ワインなど)を選ぶ
- ・夜遅くよりも早い時間に飲み始め、睡眠の質を保つ
- ・肝臓の解毒に必要な「亜鉛」を含むおつまみ(牡蠣、豚レバーなど)を意識
- ・飲酒後の水分補給をしっかり行う
妊活中におすすめの飲み物
- ・ノンカフェインのお茶(ルイボスティー、タンポポ茶、黒豆茶など)
- ・常温または白湯、水分を1.5〜2L/日程度
- ・肝臓の解毒に必要な「亜鉛」を含むおつまみ(牡蠣、豚レバーなど)を意識
- ・冷たい飲み物や甘い飲料は避け、自律神経と血流を整える飲み物を選びましょう
「妊娠に近づけられる選択」として、お酒と上手に付き合いながら、一緒に取り組んでいきましょう。
数万例超の臨床実績から導き出した方式
〔①不妊鍼灸3本柱×②不妊カウンセリング×③おうち妊活〕
・不妊鍼灸3本柱(「妊娠脈づくり」「刺さない鍼」「鍼灸おすすめ日」)
・不妊カウンセリング(「妊活情報/クリニック選び」「認活」)
・おうち妊活(「妊娠力アップおうち妊活プログラム」)
東京都新宿区西新宿7-13-7 タカラビル2F
◆◆* *・ ♪・・♪*・ *・♪*♪* ・*・ * ・*・ ・ ♪・♪■■